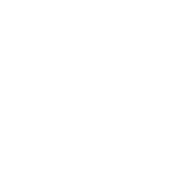月虹舎文庫
私たち40代前後の世代は、熟練の職人さんの口伝を受けられる最後の世代です。
口伝という言葉そのままに、これまで職人さんの技術や知識、経験は、活字やデータベースに残される機会は限られていました。
「真」を知る人々の英知を、精神を、僅かでもいいから受け継ぎたい。
それが叶わなくとも、せめて記録に残して、次の世代を生きる人々のヒントとなるようバトンを渡していきたい。
書籍にまとめて国会図書館に納めておくことで、いつか誰かに届くかも知れないから。
そんな思いで、「月虹舎文庫」を立ち上げます。
基本的には、きものと、きものにまつわる日本の伝統工芸に関わる分野における出版社として、自社企画「採花譜」の書籍出版と、持込企画を年に数冊ずつ、丁寧に編んでいきます。
未来は、記憶の蓄積によって作られてゆくことを信じて。
記
新着情報
月虹舎文庫、
それぞれの
楽しみ方
月虹舎文庫は、京友禅のデザイナーが立ち上げた、伝統文化・工芸の美術出版社です。
伝統文化の技術知識を次世代へ継承していくため、着物や茶道、数寄屋建築、能などの伝統文化や、それに携わる職人たちの技術知識を丁寧に取材し、口伝や英知をアーカイヴとしてまとめ、書籍に編んで参ります。
小社では自社企画だけでなく、書籍の編集企画、装釘デザインも手掛けております。
出版企画をお持ちの方は、出版企画書を添付の上、メールにてお問い合わせください。
また、着物にまつわる文化工藝を発信する場である実店舗「 salon & gallery 虹霓 」とオンラインストアにて、伝統文化や染織工芸等に特化した選書の書店と、オーナーの染織工芸の希少な蔵書を公開するご予約制の図書室「 繭隠 -mayogomori- 」を営んでおります。
良書を発刊されている著者や編集者、版元の方、伝統文化・工芸に従事されている職人さんをお招きし、課題図書と共にお話をお聞きする大人の文化講座・読書会「 荷葉日 」を不定期開催致します。
ぜひ、皆さまそれぞれのお楽しみ方を見つけてくださいませ。
online store
月虹舎文庫の出版物の他、「創造の翼を広げるための7つの配架」として下記をテーマに、きものと、日本の伝統文化、伝統工芸の良書をセレクトしております。


library
図書室「 繭隠 」
オーナーの染織工芸の希少な蔵書を公開するご予約制の図書室「 繭隠 -mayogomori- 」。
ご予約制にて、1時間ゆっくり京都・堀川北大路に在る月虹舎文庫直営店「 salon & gallery 虹霓 」にてお時間をお過ごしいただけます。
ご予約は1名様より、最大4名様まで承ります。(ご相席をお願いする場合がございます。)
季節のお茶と、紫野の美味しい和菓子屋さんのお菓子付きです。
2025年頃よりサービス開始予定に向けて現在準備中です。
自主企画
「採花譜」は、各地に残る植物染古法を研究し、京友禅の精神を承継していくプロジェクトです。
古来から在る染織に心惹かれ、染めの伝承地を尋ねると、
日本の植生の豊かさ、自然に由来した慎ましやかな文化に魅せられます。
花を育て、花に倣い、着物を染めていると、
暮らしは暦のリズムそのものなのだと感じます。
青を建てる藍の、陽差しから守る力。
黄を含む福木の、風雨を和らげる力。
赤を孕む茜の、血を清める力。
紫を宿す紫草の、悪霊を祓う力。
白を顕す絹と麻の、神の依る辺となる布。
人が布をまとう理由は、
「薬草の色を写した布で身を護るため」でした。
季(とき)と刻(とき)のあわいにたゆたい、
花と暮らし、花をまとい、暮らしを見つめてゆきたいと思います。
此君亭(しくんてい)。
竹工藝ではじめて人間国宝に選定された故・生野祥雲斎(しょうのしょううんさい)が約100年前に大分市白木の地に建てた工房兼自宅です。
いまはご当代の竹芸家・生野徳三(とくぞう)氏、寿子(ひさこ)夫人に受け継がれ、柳宗悦や黒田辰秋など、この地を訪れた文化人をもてなす迎賓館としての一面も持っています。
お茶人のお客様は、「生野祥雲斎」「生野徳三」「此君亭工房」の竹籠や竹筒をお持ちの方も多いかも知れません。
徳三先生が「彫刻」と呼ぶ独特の造形は、親子2代でそれまでの竹芸の枠を飛び越え、竹芸を芸術にまで高めたアーティストの作品として、メトロポリタン美術館に永久コレクションされるなど、世界的な評価を受けています。
きもののルーツと民俗学を研究する「採花譜」のプロジェクトで編集を担っていただいている渡邊航さんは、「日本の多様な風景に触れたい」と、それまで長く勤めておられた京都の美術出版社を退社後独立され、フリーランスライターとして大分県に移住。此君亭を紹介され、「この風景を留めたい」と将来の書籍化をおぼろげに抱きつつ、4、5年の間写真を撮り続けておられたそうです。
渡邊航さん写真・編集で此君亭の四季を綴る『此君亭好日』。
2024年3月20日発刊です。
生野祥雲斎の命日でもあり、ゆかりの古美術紹介や、普請道楽でもある徳三先生が築いてこられた、それぞれの木の物語がある框や庇を使った数奇屋建築。柞原神宮の荘園だった棚田の石垣を活かした日本庭園、寿子夫人による四季のしつらえなど、此君亭の約100年史を辿ります。
揺れる水面に時の移ろいが映え、床に四季の風が吹く此君亭の歳時記。
降り注ぐやさしい光に包まれて日々を営むこと。時を重ねてこの地で生き、老いること。人間の根源である、暮らしの普遍的な美に気付かされる272頁。
それは、生野祥雲斎から受け継ぎ親子2代で築き上げ、徳三氏と寿子夫人が高めてきた美の人生賛歌とも映るのです。
お取り扱い店
京都 京都市 salon & gallery 虹霓
京都市 KENEGAE 古美術鐘ケ江
京都市 g's gallery
京都市 大垣書店 イオンモールKYOTO店
京都市 丸善 京都本店
京都市 ふたば書房 京都駅八条口店
京都市 ふたば書房 御池ゼスト店
京都市 ふたば書房 山科駅前店
京都市 ふたば書房 洛西店
京都市 ふたば書房 大丸京都店
京都市 ホホホ座浄土寺店
京都市 京都 蔦屋書店
京都市 京都岡崎 蔦屋書店
京都市 恵文社一乗寺店
京都市 珈琲山居
京都市 想 sou
大分 臼杵市 見星禅寺 星月庵
臼杵市 うすき皿山
臼杵市 明屋書店臼杵野田店
別府市 別府竹工芸とクラフトショップ
別府市 別府 おぐら
別府市 器ギャラリーhangi
別府市 bamboo bamboo
別府市 SELECT BEPPU
別府市 竹工芸山正
別府市 HAJIMARI Beppu
大分市 晃星堂書店
大分市 古美術花元
大分市 イシカワ珈琲
大分市 器や しば
大分市 Bareishoten
大分市 タピエス
大分市 リブロ大分 わさだ店
大分市 リブロ大分 トキハ店
大分市 くまざわ書店 大分明野店
大分市 明屋書店フリーモールわさだ店
中津市 三光堂書店
杵築市 杵築市観光協会
杵築市 お茶処とまや
由布市 ある風景
由布市 金門坑。
竹田市 但馬屋老舗
北海道 札幌市 MARUZEN&ジュンク堂書店
白老郡 またたび文庫
青森 弘前市 まわりみち文庫
岩手 盛岡市 BOOKNERD
東京 杉並区 本屋Title
杉並区 文禄堂 高円寺店
杉並区 サンブックス 浜田山
新宿区 かもめブックス
新宿区 紀伊國屋書店 新宿本店
千代田区 丸善 丸の内本店
千代田区 丸善 お茶の水店
千代田区 東京堂書店 神田神保町店
千代田区 南洋堂書店
港区 文喫 六本木
中央区 銀座 蔦屋書店
渋谷区 青山ブックセンター本店
渋谷区 Shibuya Publishing & Booksellers
渋谷区 代官山蔦屋書店
世田谷区 BOOKSHOP TRAVELLER
世田谷区 二子玉川蔦屋家電
豊島区 ジュンク堂書店 池袋本店
立川市 ジュンク堂書店 立川高島屋店
立川市 オリオン書房ノルテ店
多摩市 MARUZEN 多摩センター店
府中市 マルジナリア書店
目黒区 ブックファースト自由が丘店
三鷹市 啓文堂書店 三鷹店
武蔵野市 ジュンク堂書店 吉祥寺店
墨田区 YATO
品川区 フラヌール書店
神奈川 藤沢市 ジュンク堂書店 藤沢店
横浜市 ブックファースト 青葉台店
鎌倉市 たらば書房
鎌倉市 くまざわ書店 大船店
埼玉 川越市 ブックファーストルミネ川越店
千葉 柏市 くまざわ書店 モラージュ柏店
新潟 新潟市 ジュンク堂書店 新潟店
富山 南砺市 カフェトリアン
福井 福井市 わおん書房
今立郡 小豆書房
長野 松本市 ジュンク堂書店 丸善 松本店
岐阜 多治見市 ひらく本屋 東文堂
岐阜市 丸善 岐阜店
美濃加茂市 HUT BOOKSTORE
愛知 名古屋市 名古屋みなと 蔦屋書店
名古屋市 TOUTEN BOOKSTORE
西春日井郡 紀伊國屋書店 名古屋空港店
和歌山 東牟婁郡 らくだ舎
大阪 大阪市 ジュンク堂書店 大阪本店
大阪市 ジュンク堂書店 天満橋店
大阪市 紀伊國屋書店 梅田本店
大阪市 ジュンク堂書店 難波店
豊中市 豊文堂
兵庫 淡路市 島の本屋
神戸市 ジュンク堂書店 三宮店
岡山 久米郡 ジリリタ書店
広島 広島市 READAN DEAT
広島市 ジュンク堂書店 広島駅前店
山口 宇部市 工夫舎
福岡市 ジュンク堂書店 福岡店
福岡市 本と羊
北九州市 みぢんこ
宗像市 umiba books
大牟田市 taramu books & cafe
スイス Onoda Japanese Store Craftsmanship and harmony
美術館、博物館
図書館
東京 千代田区 国立国会図書館
江東区 芝浦工業大学 大宮図書館
世田谷区 日本女子体育大学附属図書館
小金井市 小金井市立図書館
日野市 明星大学図書館
神奈川 鎌倉市 鎌倉市玉縄図書館
静岡 藤枝市 藤枝市立図書館
大阪 豊中市 豊中市立岡町図書館
東大阪市 大阪府立中央図書館
高槻市 高槻市立中央図書館
兵庫 三田市 関西学院大学 神戸三田キャンパス
大分 大分市 大分県立図書館
由布市 由布市立挾間公民館
杵築市 杵築市立図書館
豊後大野市 豊後大野市図書館
速見郡 日出町立図書館
熊本 菊池市 菊池市中央図書館
徳島 徳島市 徳島県立図書館
お取引のご案内
月虹舎文庫の出版物をお取り扱い頂ける書店様、小売店様を募集しております。
書籍をお取り扱い頂けます皆様には、以下の条件にてお取引を承ります。
・販売サイト 版元ドットコム、BOOKCELLAR、一冊!取引所
・直接取引 上記外からの直接のお問い合わせは、下記表示の注文書にご記載の上、
PDF添付メールまたはFAXにて承ります。
□ 小社直取引の場合は、買取のご協力をお願いいたします。
□ 直販|掛率:買切 70%
□ 送料|一律550円。5冊以上のご注文で送料無料。
□ 発送|2~3営業日内に発送します。( 土日祝発送休 )
□ 一冊!取引所からのご注文は「一冊!決済」ご利用可能です。( 買切 73% )
□ 直取引のご請求について|末締め、翌月末払い
( 振込手数料はご負担をお願いしております)
□ 同封のご請求書到着月の翌月末までにお支払いをお願いいたします。
□ お支払いのタイミングが上記と異なる場合や、
お振り込み名義が「貴店名」と異なる場合はご注文時にお知らせください。
□ 振込先|三井住友銀行|京都支店|普通|9453107|株式会社月虹舎|カ)ゲッコウシャ
□ 弊社は適格請求書発行事業者です(登録番号 T7130001057466)。
・取次 下記表示の注文書にご記載の上、トランスビューの取扱いで納品いたします。
□ 直接取引ルート|トランスビュー代行(返品随時可)。
□ 取次ルート|八木書店→日販、トーハン他可。(買切・返品不可)。
トランスビューとのお取引がないお店からのご注文は、小社からご連絡いたします。
□FAXはこちら→ 0120-999-968 ( トランスビュー )
その他、ご不明な点がございましたらコンタクトフォームよりお気軽にお問い合わせください。
ご検討の上、何卒ご高配を賜れますと幸いです。
書店様向けご案内
いつも月虹舎文庫の商品をお取り扱いいただき、ありがとうございます。
書店様へ向けて、注文書や、ポップ、ポスターなどの販促物をご用意いたしました。
ダウンロードしてご活用くださいませ。
2024/3/20 発売
渡邊 航 著
ISBN978-4-9912638-1-1 C0072 ¥2800E
特設HP:此君亭好日
Instagram:@shikuntei_koujitsu
お問い合わせ
営業時間
open 11:00-17:00
close 日月祝(不定休)
tel: 075-286-4815
fax: 075-320-2804
mail: info@gekkosha.kyoto
Instagram:@gekkosha.bunko_books
〒603-8215
京都府京都市北区紫野下門前町66番地8
月虹舎文庫( 株式会社 月虹舎 )